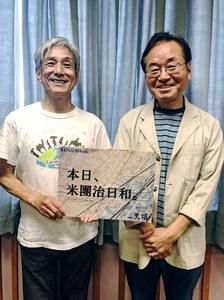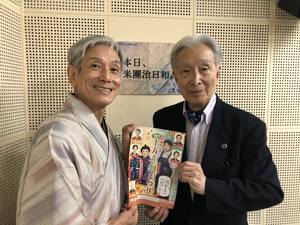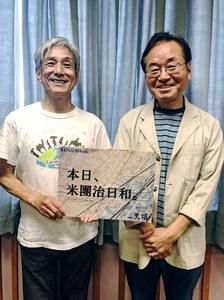今回のゲストは桂ざこば筆頭弟子、四代目桂塩鯛 (かつら しおだい) さんです。
塩鯛さんは京都府出身。
立命館大学経営学部を中退後、昭和52年に当時桂朝丸として活躍されていたざこば師匠の元に入門、落語の世界へ。
師匠の朝丸にちなんだ桂都丸の名で活躍後、2010年に四代目桂塩鯛を襲名しました。
師匠の名 ざこばとは 雑魚 (ざこ) の場、ということで魚市場 (うおいちば) のこと。
塩鯛とは腐らないように塩をした、いわば鯛の干物のこと。
ざこばの弟子にはぴったりの名前です。
師匠譲りの迫力のある落語で、特に「替り目」「らくだ」などの人情味のある噺やお酒の噺を得意とする塩鯛さん。古典落語はもちろんの事、新作落語にも積極的に挑んでいます。
弟子は「米紫」「鯛蔵」「小鯛」の3人。
年が明けたら古希記念の独演会も控えています。
五代目桂米團治との噺家対談。
噺家同士のテンポ良い対談をお楽しみください。

今回のゲストは、京都市東山区安井に鎮座する安井金比羅宮 (やすいこんぴらぐう) の鳥居肇宮司です。
神社の祭神は崇徳天皇(すとくてんのう) 大物主神(おおものぬしのかみ) 源頼政公(みなもとのよりまさこう)。
崇徳天皇が一切の欲を断ち切り、讃岐の金刀比羅宮 (ことひらぐう) にこもられたという故事により、神社は断ち物の祈願所として信仰されました。
安井金比羅宮は縁結びとは逆に、悪縁 (あくえん) を絶ってくださる神社です。
男女の縁はもちろん、病気、酒、煙草、賭事など、全ての悪縁を切り、良縁に結ばれるという御利益がうたわれています。
境内にある「縁切り縁結び碑 (いし)」は、正面からくぐると悪縁を絶ち、裏面からくぐれば良縁があるといわれています。
毎年落語会を開くなど米朝一門とのかかわりも深い安井金比羅宮。
米團治が新年掲げられる大絵馬の原画を奉納しているご縁もあります。
新しい年を迎えるにあたり、悪縁を切り、良縁を招くありがたい神様のお話をうかがいましょう。

今回のゲストは声楽家カウンターテナー 藤木大地さんです。
藤木さんは1980年宮崎県生まれ。
東京藝術大学音楽学部声楽科を卒業、新国立劇場オペラ研修所を修了。
さらにウィーン国立音楽大学大学院を修了。
藤木さんが注目を浴びたのは2017年4月、オペラの殿堂・ウィーン国立歌劇場で『メデア』ヘロルド役での鮮烈デビューでした。これは日本人、そして東洋人のカウンターテナーとしても史上初の快挙でした。
彼の歌声はウィーンの聴衆からも熱狂的に迎えられ、当然日本国内でも"選ばれし声が伝える歌の魂" "神秘の歌声"などと大絶賛されました。
藤木さんのレパートリーはバロックからコンテンポラリーまで幅広く、主要オーケストラとの公演や各地でのリサイタル、アルバムのリリースなど。デビューから現在まで常に話題をさらう、日本が世界に誇るアーティストのひとりです。
オペラを愛する米團治が誰よりも楽しみにする対談です。
どうぞお楽しみに。

今回のゲストは、KBS京都ラジオ「スマイル・オン・アース」に出演中の株式会社ボーダーファミリー代表 曽和ローズさんです。
ラジオ、テレビで長年活躍されている曽和さんはABCアナウンサーを経て、しゃべり稼業48年。現在もナレーション、MC、ウグイス嬢、講師等活動の場はますます広がっています。ほかにも芝居演劇、動物愛護ボランティア、裏千家茶道、着物着付け講師など多忙な毎日。米團治とは共演経験もあり、お互い切磋琢磨した仲です。
今回は彼女が今までかかわった実力派の声のプロが集結して実現した、リーディング劇「最後の薬...は?」を紹介していただきます。
もう一人のゲスト塩見智子さんはアナウンサー事務所「有限会社ビー・グラッド」代表取締役。ラジオ番組や司会、ナレーションで歩んだキャリアは46年。言葉と声のプロフェッショナル、トータルスピーチコンサルタントとして活躍中です。
彼女も米團治とは旧知の仲。
一緒に、リーディング劇についての思いと、若かりしころの思い出を米團治と共にたっぷりと語っていただきましょう。

今回のゲストは京都島原に店を構える老舗料理店「島原 乙文」4代目若主人
木村一智(かずとも)さんです。
「島原 乙文」は花街として発展してきた京都・島原で、日本に唯一残る、太夫を抱える置屋 兼 お茶屋「輪違屋」への仕出しでも知られる京料理の名店です。
4代目を継ぐ一智さんは1988年生まれ。
大学卒業後は社会人として他業種の企業に就職後、25歳より乙文で3代目に師事し料理を始めました。料理人として励みながらお店と島原の魅力をより多くの方に知ってもらおうと「日本三大遊郭・島原を若主人と共に巡る旧花街歴史さんぽ −四季折々の京ランチ付き−」を企画。
島原で生まれ育った若主人一智さんからこの地の歴史を学び、旬の味覚を詰め込んだ華やかな京ランチを堪能。食後は若主人が自ら旧花街を巡る街歩きをナビゲート。内外の人々に今に残る島原の風情溢れる風景と文化を楽しんでいただきます。
対談ではそんな楽しいツアーの紹介とお店のおもてなしなど、
存分に語っていただきましょう。

今回のゲストは俳優で舞踏家の林与一さんです。
現在京都南座で催されてる「松竹上方喜劇まつり」にご出演中ということで
今年もご登場いただきます。
林さんは1942年生まれ、大阪府の出身です。
曾祖父は初代中村鴈治郎、祖父・父も歌舞伎役者という家系に生まれ、
ご自身も1958年、大阪歌舞伎座で初舞台を踏みました。
NHKの大河ドラマ「赤穂浪士」堀田隼人役で脚光を浴び、「人形佐七捕物帳」
「必殺仕掛人」など、時代劇スターとして様々な作品で活躍。
舞台では自身の座長公演の他、数多くの女性座長の相手役を務め、
特に美空ひばりさんとは黄金コンビとして人気を博しました。
舞踏家としては祖父が1951年に創始した日本舞踊「林流」の宗家でもあります。
現在は、自身の芸能人生を語る講演会やワークショップ、トークショーなどにも
積極的に取り組まれています。
米團治とは1年ぶりの対談、大いに楽しんでいただきましょう。
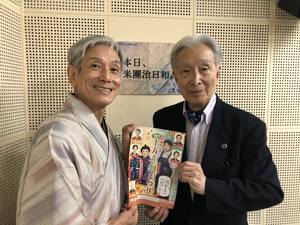
今回のゲストは平安神宮 権禰宜 室川豊史さんです。
明治3年、幕末の戦乱で荒廃した京都から明治天皇が東京へ行幸。事実上の東京遷都でしたが、正式な発表はなく、京都の人々は「天皇さんはすぐに帰ってきやはる」と信じていました。
しかし、多くの公家や商家も天皇とともに東京へ去り、京都の人口は激減。
それでも京都は復興への道を歩みだします。平安神宮の創建もそのひとつです。
平安遷都1100年を機に、京都を開いた桓武天皇を祭神とする神社の創建が企画され、
明治28年4月、京都の全市民を氏子とする平安神宮が誕生。
その後、皇紀2600年にあたる昭和15年には平安京最後の天皇、
第121代孝明天皇のご神霊が合わせ祀られました。
平安神宮の大祭、時代祭りの時代行列は京都におわした最初の帝 桓武天皇と、
最後の帝 孝明天皇の神霊が京都の変遷と繁栄をご覧になるために進む
御鳳輦(ごほうれん)のお供をする祭列です。
対談では平安神宮創建から時代祭りについて、
私たちが知っているようで知らないエピソードをお聞きかせいただきましょう。

今回のゲストは噺家の桂力造さんです。
力造さんは1978年、大阪府阪南市生まれ。
2000年5月 桂ざこば師匠に入門しました。
桂ひろばの名で2000年5月 箕面メイプルホール「ざこばの会」にて初舞台。
「第1回 桂ひろば独演会」は2021年4月、天満天神繁昌亭にて。
寄席のほかにも学校やお寺、病院、老人ホームなどで積極的に落語会を行っています。
そして今年3月20日、二代目桂力造を襲名しました。
同じざこば師匠の弟子ちょうばが桂米之助、そうばが桂惣兵衛と、
三人同時襲名が話題となりました。
趣味は手品、ツーリング、一人旅という力造さん。
バイクで各地を訪問するツーリング落語会も彼のライフワークです。
対談では師匠の思い出や襲名のエピソードから名跡のお話。
また10月にも開催される三人同時襲名披露公演についても語っていただきます。
同時襲名の三人の関係や互いに切磋琢磨する意気込みなどにも迫ります。

今回のゲストは京都在住のピアニスト、竿下和美(さおした かずみ)さんです。
竿下さんは京都市立堀川音楽高校を経て、京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専修を卒業。
卒業後は国内外で積極的に活動、多くのコンクールで優秀な成績を収められました。
ソロ活動とは別にサックスとのユニットやアンサンブルピアニストとしても活躍。
「次世代の音楽家を育てること」こそ、大切な使命だとNPO法人京田辺音楽家協会理事長としてコンクールの主催、また指導者として後進の育成にも力を注いでおられます。
2023年に肺腺癌を発症、余命宣告を受けました。
それでも治療を続けながら病院、福祉施設などで同じ病気の方への希望になるなら、抗がん剤治療で苦しむ方の気持ちを少しでも軽くできるならとボランティアでのピアノコンサートを積極的に行われています。
がんと向き合いながら、音楽の力で「希望」を届ける竿下さんの活動と、強い思いをお聞かせいただきます。

今回のゲストは噺家 三代目桂文之助さんです。
桂文之助さんは1956年、神戸市生まれ。
京小学校の頃から落語に興味を持ち、桂枝雀に憧れ、高校3年生の時に弟子入りを志願。
卒業後の1975年3月に南光、雀三郎(じゃくさぶろう)につぐ三番弟子として
入門が許されました。
最初の芸名は雀松。船弁慶の「雀のお松」に由来し、大師匠の桂米朝が命名しました。
「雀の会」にて初舞台。
以降古典落語のほか、狂言師との共同制作に取り組むなど幅広く活動されています。
2013年10月6日、83年ぶりの復活となる桂文之助を正式に襲名、
サンケイホールブリーゼにて披露公演を行いました。
米團治とはほぼ同世代、二人の落語談義をぜひお楽しみください。